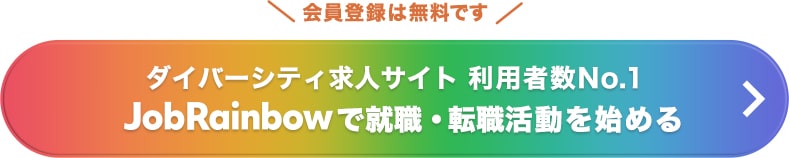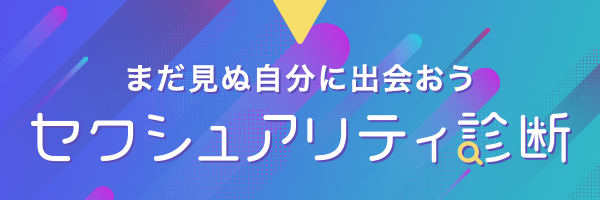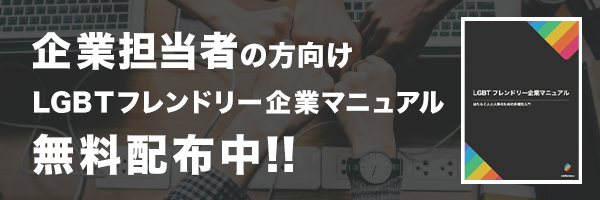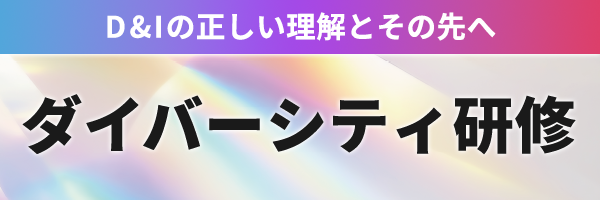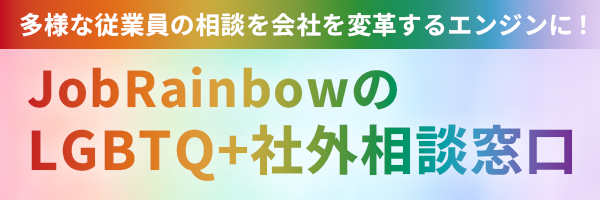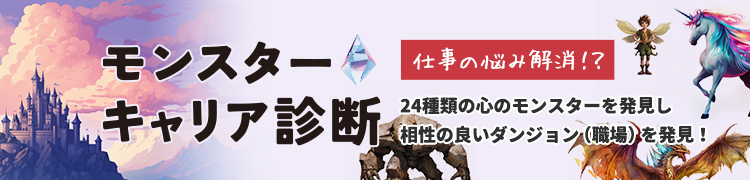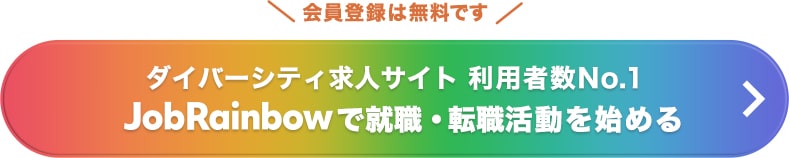
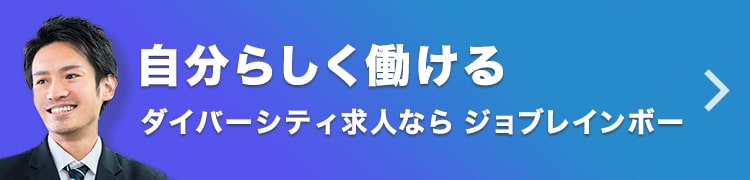
「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBが追求するDEIB推進の現在地と未来【後編】

「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBが追求するDEIB推進の現在地と未来【前編】
前編では、JTBのこれまでのDEIB推進への想いや歩みをご紹介しました。
後編では引き続き株式会社JobRainbow 代表取締役 CEO 星賢人が、JTBが取り組んでいる具体的なDEIB推進施策や効果的なDEIB推進方法について、JTB常務執行役員DEIB担当 人財開発担当 働き方改革担当(CDEIBO)の髙﨑さんに伺いました。
休暇取得率が倍増?! 活用される制度づくりのポイント

※以下敬称略
星:JTBでは、性別移行のための通院の有給扱いや、同性カップルでも結婚休暇が取得できる制度、女性の健康課題を支援する法人向けプログラムの導入など、多くの先進的な取り組みをされています。こうした取り組みに関して、社内の評判や、制度を実際に利用されている方の声はいかがでしょうか。
髙﨑さん(以下、敬称略):どれも非常に好評です。まず、「生理休暇」は名称を「ウェルネス休暇」へと変更。取得事由も拡大し、生理だけでなくホルモン療法、性別適合手術、不妊治療、そして健康診断の再検査なども対象にしました。これまで再検査に行く際は年次有給休暇を使うしかありませんでしたが、それをウェルネス休暇の対象にしたのです。この名称と事由の変更によって、取得率は2倍近くに上昇。「生理で休みます」とは男性の上司に言いにくいけれど、「ウェルネス休暇で休みます」なら言いやすい、という声があり、もっと早く変えればよかったと思ったほどです。
女性の健康課題支援プログラムも、多くの社員が登録・利用しています。出張や添乗が多い仕事柄、体調の波があることに不安を感じるメンバーも多かったのですが、自身のバイオリズムを知り、対策することで、「体調不良で寝込むことがなくなった」という声も聞いています。
その他、就業規則上の「配偶者」の定義を「パートナー」に変えることで、当社が決められることはすべて、同性パートナーの方にも適用できるようになりました。例えば、慶弔金や単身赴任手当なども対象です。
星:単身赴任手当まで対象となるのはすごいですね。費用もかかるため、なかなか踏み切れない会社が多いと聞きます。
顧客に向けたDEIB領域の取り組みについて、特に直近のものを伺ってもよろしいですか。
髙﨑:ユニバーサルツーリズムという観点から、正しいご案内ができるように知識浸透と情報の集約化、困ったときの相談窓口の設置を行っています。間違ったご案内をしてしまうと時として重大な事故につながる可能性があるため細心の注意を払っています。
個人のお客様向けにご利用いただける商品としては、お客様が着用したいものを選んでいただけるハワイでのウェディングフォトプランがあります。タキシード×タキシード、ドレス×ドレス、タキシート×ドレスからお客様の好きな衣装を選んでいただける内容となります。法人向けでは、他社と協業しながら日帰り~数日間参加するセミナープログラムを開発・販売しています。
日本社会全体として、より一層DEIB推進が必要だと考えています。 私たちも、「交流」という側面から、その後押しができればいいなと思っています。

星:私もゲイの当事者なので、フォトウェディングはすごく素敵だなと感じました。日本では現在同性婚ができないため公的な関係を証明できないですし、人によっては式を挙げても親族を呼べないこともあります。そんな中で形として残しておきたいと思ったとき、写真として残せることはとても意義のある取り組みだと思います。
非財務の取り組みを財務価値へつなげる、JTB流 DEIB推進の進め方

星:DEIB領域において、経営層との合意であったり、各種の指標、KPIの測定評価が難しいという声を他社から我々も日々いただいています。どのように設計をされたのか、また運用される時にどうやってそれを浸透させていけたのか、お伺いしてもよろしいですか。
髙﨑:一番のポイントは、「DEIB推進はその場のノリやトレンドの追っかけでやっているものではない」ということを、きちんと証明することです。また、「どうすれば会社の機関決定に組み込めるのか」も、すごく大事だと思います。 そのためには会社のトップを巻き込むことが必要です。当社CEO の山北もすごくこの活動に熱心で、TokyoPrideにも来ています。トップの協力を得つつ、どうやって皆さんをまとめていくかということかもしれないですね。
具体的に当社で何をしたかというと、「何のためにDEIBを進めるのか」という構造図をしっかりと作り、それを経営会議、そして取締役会で承認してもらいました。 そうすると、施策の途中で反対意見が出た時に、「取締役会の時に『承認』しましたよね」「経営会議の時もちゃんとお話をしましたよね」と言えるようになる。これが組織では絶対重要だと考えています。 私個人が「これを進めます」ということではなく、会社の機関決定で正式に承認を得て全員で進めるということですね。そのための準備は入念にやりました。
私たちのゴールは当社のビジョンそのものです。 ビジョン達成に向けて、社員と経営で一緒に作った「信頼を創る」「挑戦し続ける」「笑顔をつなぐ」という「ONE JTB Values」を掲げています。
非財務領域の取り組みですが、これをやることが将来的に財務価値に繋がります。 そして、ビジョン達成のためには社員のエンゲージメントが高くないといけませんし、社員のベクトルと経営のベクトルが合致していなくてはいけません。 それを実現する企業風土を醸成するには、DEIBが必要で、そのベースには人財戦略があります。 これを「DEIB戦略」「人財戦略」という言い方をしています。
星:一番上にあるビジョンから、どんどんそれをブレイクダウンしていく感じですね。JTB社の取り組みで非常に印象的なのが、サーベイの結果やKPI指標を外部に明確に公開している点です。この辺りはいかがでしょうか?
髙﨑:KPI指標の公開は2023年から実施しています。重要なことは、今結果が目標に達しているかではなく、前に進むかどうか。 例えば今目標が70で、実際は50だとします。未達だから公開しないのではなく、現状を公開したうえで成長をみせていく。今は50でも来年60、そのうち70になればいいよね、という考えです。
DEIB推進が難航するポイントの一つが「非財務領域」であること。 そこを補うために、「DEIB推進が職場環境を改善し、プロセスのイノベーションもプロダクトのイノベーションも変わっていくよね」「外部評価が上がってくる。これで将来的に絶対的に財務価値につながる」ということを数値として可視化しながら説明する。 これを社内に向けて実施していく予定です。
社員に説明するときは、この担当は誰々ですと顔写真も出して、「こんなことやっています」と、具体的にしめす方法で紹介しています。そうすることで、取り組みを身近に感じられ、誰の責任で動いているのかもわかりやすくなります。
星:今後のDEIBに関する取り組みについて、何か計画していることや想いはありますか?
髙﨑:先ほどのお話と少し被りますが、「非財務価値を向上させることが、将来、財務価値の向上にもつながること」を可視化したいなと思っています。とてもチャレンジングな挑戦です。
例えば、組織風土改革が進んでいる部門は、財務数値上も良い結果が出ているとか、様々な仮説を立てて検証しています。 財務的価値は売上だけでなく、例えば社員の離職率や意識調査にも表れてくるので、それらをどうやって数値化・可視化していくかというものです。
更に、当社では「Smile活動」という活動をしています。約 2万人の社員がいて、国内も47都道府県すべてに店舗があるのが当社の大きな強みです。 一方で、これだけ組織が大きいと、情報の伝達などにも工夫が必要です。そこで、各組織に組織風土を改革するために設置されたのが「Smile委員会」です。 その委員長は、各支店の個所長が「この人に任せたら自分のところの組織は良くなる」という人を指名しています。 新入社員のところもあれば、課長のところもある。年齢層や性別など、バックグラウンドはバラバラです。
施策をスムーズに進めるためには、この「Smile委員長」が動きやすいか、孤独ではないかが大きなポイントです。その重要性を、Smile委員長自身はもちろん、個所長やミドルマネジメント層が理解しているかに注目しています。ミドルマネジメント層は、会社の財務的な数字に大きな責任を持っています。DEIB推進が大切だとわかっていても、財務に直結する施策の優先順位が上がりがち。 ですが、DEIB推進と財務数値は絶対リンクしていると思っていますので、このミドルマネジメント層へのアプローチがポイントだと考えています。
また、当社はグローバルに社員がおりますので、JTBグループ全体、グローバルとしてこの活動をどう進めていけるのかにも注力したいですね。ヘッドクォーターがアメリカ・アジア・ヨーロッパにあるのですが、先ほどのDEIBステートメントをそれぞれの事業計画に組み込んでいます。 これまで以上に多様な取り組みが始まっているので、どう進化していくかすごく楽しみです。
星:日本のみならず、世界にも活動が広がっているのですね!日本では日々インバウンド需要が高まっており、新たなインクルージョンの道を模索していく段階にあるのかと思います。最後の質問ですが、長年ツーリズム業界のトップランナーとして走り続けているJTBの、今後のツーリズム業界とDEIB推進についての思いや展望についてお伺いします。
髙﨑:まず、ツーリズム産業は非常に裾野の広い業界です。 ホテル、交通機関、お土産物屋…さらに、そこに関わる生産者の方々も含めると本当に幅広いです。
その中で、関わる人それぞれが自身の多様性も認識をして、他の人の多様性も認めて交流をしていくと、大きな効果が生まれると信じています。 当社のやり方を発信していくことで、DEIBの考え方や組織風土の作り方、KPIや数値の部分も含めて、微力ではありますがDEIBを推進されるみなさまの参考となれば良いなと思います。業界全体で盛り上げたいな、と心から思っています。

※本記事初出 2025年8月28日
本記事でご紹介する情報は、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。
各記事の日付はシステム上の更新日付であり、執筆時の日付と異なる場合があります。
各記事は、執筆当時の情報に基づいて作成されています。そのため、最新の情報とは異なる内容や、現在の価値観と相違する表現が含まれている場合がございます。ご了承ください。
また、当社は、読者様が本記事の情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。本記事の内容の正確性や個別の状況に関するご判断は、読者様ご自身の責任において行っていただき、必要に応じて専門家にご相談ください。