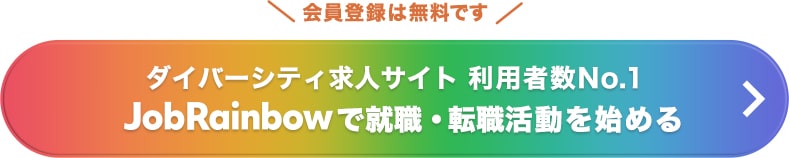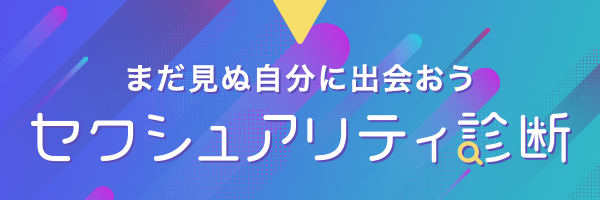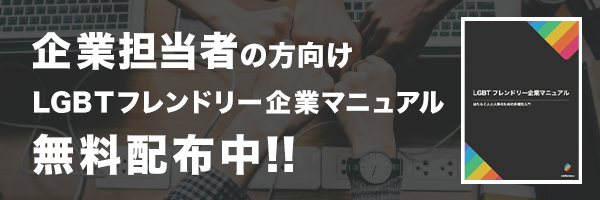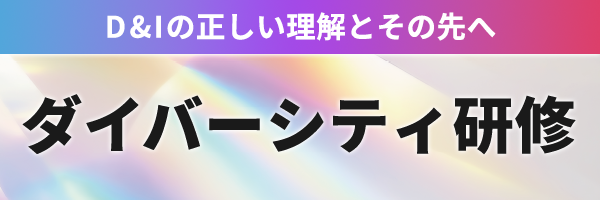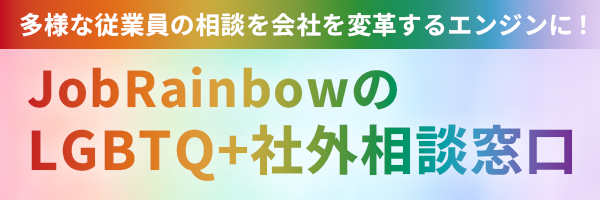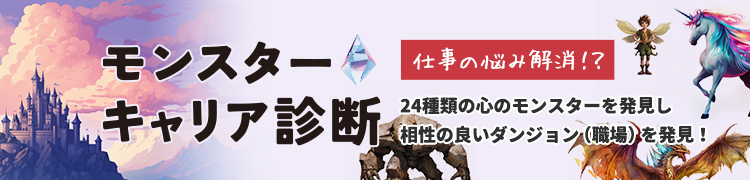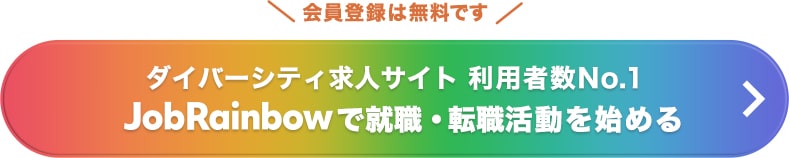
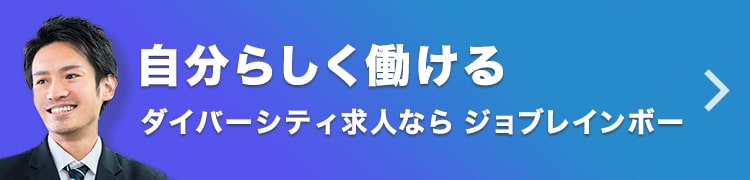
【2026年最新】同性パートナーと生命保険完全ガイド〜受取人指定から税金対策まで〜

「この人と、一生を共にしたい」。そう心に決めたとき、二人の未来を明るく描く一方で、「もしも、何かあったら……」という漠然とした不安がよぎることはありませんか? 特に、お金や保険のこととなると、どこから手をつけていいのか分からず、立ち止まってしまう方も少なくないかもしれません。
「同性パートナーは生命保険の受取人になれるの?」「保険に入るメリットは?」「パートナーシップ証明書があれば大丈夫?」
そんな、あなただけの悩みじゃない疑問に、このガイドが一つずつお答えしていきます。
この記事が、あなたの漠然とした不安を解消し、パートナーとの未来を安心して築くための確かな一歩となることを願っています。さあ、一緒に「ふたり」の人生の地図を描いていきましょう。
同性パートナーが直面する「生命保険」の壁

日本の法制度における「結婚」の壁
同性カップルがパートナーとの未来を考える上で、まず最初に直面するのが、日本の法制度における「結婚」の壁です。現在の日本では、法的に同性婚は認められていません。この一つの事実が、生命保険をはじめとする多くの分野で、異性カップルにはない複雑な課題を生み出しています。
最も大きな問題の一つが、同性パートナーは民法上の「法定相続人」にはなれないという点です。これは、たとえ長年連れ添ったパートナーであっても、片方が亡くなった際に、その財産は法定相続人である親族(子、親、兄弟姉妹)に引き継がれることを意味します。
そのため、相続の発生により、亡くなったパートナー名義の自宅が相続人のものになって明け渡しを求められたり、二人で協力して築いた財産がすべて相続人のものとなったりといった事態が起こり得るのです。
なぜ生命保険が重要なのか
このような法的な壁があるからこそ、同性カップルにとって生命保険は特に重要な意味を持ちます。
生命保険の保険金は、受取人に指定された人の固有の財産であり、遺産分割の対象にはなりません。たとえ被相続人が遺言書を残していなかったとしても、相続人の手に渡るようなことは起きないのです。
つまり、同性パートナーを受取人に指定できれば、確実にパートナーに財産を残すことができる手段の一つとなるのです。
同性パートナーを生命保険の受取人にする方法

変化してきた生命保険業界
少し前まで、同性カップルの相手を生命保険の受取人にすることはできませんでした。生命保険の受取人は原則として「配偶者または二親等以内の親族(父母や子ども、孫など)」とされており、保険本来の目的とは異なる保険金詐欺などを防止するため、受取人が厳しく限定されていたためです。
しかし、2015年に東京都渋谷区、世田谷区で「パートナーシップ制度」が導入されたことを契機に、状況は大きく変わりました。同年、ライフネット生命が初めて同性のパートナーを受取人に指定することを可能にし、その後、同様の取扱いをする保険会社は増加。現在では10社以上で同性パートナーを受取人とすることができるようになっています。
必要な書類は?パートナーシップ証明書は必須?
結論から言うと、現在、多くの生命保険会社で、同性パートナーを保険金の受取人に指定することが可能です。
ただし、手続きには各保険会社が定める条件をクリアする必要があります。一般的には、次のいずれかの書類の提出を求められるケースが多いようです。
- 自治体が発行する「パートナーシップ証明書」の写し
- 住民票(同居期間の証明)
- 公正証書(準婚姻契約など)
保険会社によっては、戸籍上の配偶者がいないことや、一定期間以上の同居・生計を共にしていることなどを確認するため、面談が必要となることもあります。
注意すべき点は、契約条件が保険会社によって大きく異なることです。 同性パートナーを受取人とできない保険会社もまだ存在しますし、一定の同居期間が条件になる場合もあります。パートナーシップ証明書が必須の保険会社もあれば、特に必要としないところもあるなど、条件は一律ではありません。
受取人指定が可能な保険会社の選び方
生命保険会社を選ぶ際には、以下のポイントを確認しましょう。
- 同性パートナーを受取人に指定できるか:まず基本的な対応可否を確認
- 必要書類の条件:パートナーシップ証明書の要否、同居期間の条件など
- サポート体制:死亡診断書取得のサポートなど、もしもの時の対応
- 契約時の面談の有無:面談が必要な場合、その内容や所要時間
契約の際には、これらの点についてしっかり確認するのがいいでしょう。
同性パートナーを生命保険の受取人にする3つのメリット

同性パートナーを生命保険の受取人に指定することには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
メリット1:残されたパートナーの生活保障
主婦(主夫)として相手を支えていた場合、先立たれた後の生活が大変になるのは、法律婚の「夫婦」と同じです。まとまった保険金があれば、家賃や住宅ローン、老後の資金などに充てることができます。
リビングニーズ特約など、生前に保障を受け取れる特約にも注目しましょう。被保険者の余命が6か月以内と判断された場合、死亡保険金の一部または全部を前もって受け取ることができる特約です。これにより、最期の時間をパートナーと穏やかに過ごすための資金として活用できます。
メリット2:相続税の納付資金の確保
被相続人の財産が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、超えた分に相続税がかかってきます。遺産額の多くを土地や家などの評価額が占める(=現金が少ない)場合、現金一括納付が原則の相続税の納付に困難をきたすかもしれません。
生命保険の保険金は、その支払いに充てることができます。また、死亡時だけでなく、病気や介護状態になったときのための保障も検討してみましょう。貯蓄型の保険や、介護保険、医療保険などを組み合わせることで、二人の老後も安心して支え合うことができます。
メリット3:「遺留分侵害額請求」への備え
法定相続人には「遺留分」(相続人が最低限受け取れる遺産の割合)が認められています。例えば、被相続人の親が生きていれば、遺産の3分の1は受け取る権利があります(侵害した部分について請求があれば、応える必要があります)。
遺留分を侵害する遺言書が残されていた場合には「遺留分侵害額請求」を起こされて、現金の支払いに困るケースも考えられます。保険金があれば、それに充当することができるでしょう。
この場合、受取人は親などの相続人ではなく、必ずパートナーにしておく必要があります。 相続人に保険金が支払われても、相続財産の遺留分はなくならないからです。
健康上の理由で諦めていた方へ
「過去に病気を患ったことがある」「性別適合手術やホルモン療法を受けている」といった理由で、生命保険の加入を諦めていた方もいるかもしれません。
従来の生命保険は、健康状態の告知を厳格に行い、性別適合手術やホルモン療法を「治療中」とみなすため、加入が難しいケースが多くありました。また、ゲイに多いHIV陽性の人や、ホルモン投与を受けているトランスジェンダーの人などは、健康リスクを理由に契約を結べないこともあるのが実情です。
しかし、このようなハードルを乗り越えるためのサービスも生まれています。たとえば、R&C株式会社が提供する「パートナー共済」は、HIV陽性の方や、性同一性障害(GID)のホルモン療法中でも加入できることを明確にしています。さらに、PEP(曝露後予防)やPrEP(曝露前予防)といった、HIV感染予防に関する診療費用の一部を補助するサービスも提供しています。
こうしたサービスは、単に「保険を提供する」だけでなく、これまでの保険業界がデータ不足や理解不足から見過ごしてきたセクシュアリティ特有の健康課題にも深く向き合っています。こうした取り組みは、当事者への理解を深め、より多くのデータが集まることで、今後、保険業界全体の在り方を変えていく可能性を秘めていると言えるでしょう。
LGBTQ+フレンドリーな保険代理店R&C株式会社の「パートナー共済」が生まれたきっかけ
同性パートナーが受取人の場合の税金

同性パートナーを受取人とする生命保険が増えたことで、生活不安などに対処できる手段が広がりました。ただ、LGBTQ+の人たちに対する法的な面をはじめとする「不平等」は依然として残されており、特に税制面では注意すべきことがあります。
生命保険料控除が使えない
生命保険の保険料は年末調整や確定申告の際に生命保険料控除の対象になるのですが、それは親族が受取人の契約に限られます。 同性パートナーが受取人の場合には、この控除が受けられず、所得税と住民税が軽減されることはありません。
さらに、所得税の「配偶者控除」や社会保険の「健康保険の扶養家族」といった、法律婚が前提となる国の制度は、同性カップルには原則として適用されません。これにより、経済的にどちらかがパートナーを支える場合でも、税制上のメリットや社会保障の恩恵を受けることが難しいのが現状です。
相続税の非課税枠(500万円×相続人数)が適用されない
生命保険の保険金には、「500万円×法定相続人の数」という相続税の非課税枠があります。例えば相続人が3人いれば、1,500万円までは相続税がかからず、それを上回った金額が課税対象になるのです。
しかし、同性パートナーは法定相続人ではありませんから、この非課税枠は使えません。 受け取った保険金の全額が、相続税の課税対象とされます。
非課税枠のある生命保険は、現金で相続させるよりも有利なため、相続税対策として使われることもあります。同性パートナーの場合、相手のために活用できる生命保険は増えたものの、そうした税制面でのメリットは期待できないのです。
配偶者の税額軽減も対象外
法律上の配偶者には、相続した遺産の「1億6,000万円まで」と「法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは相続税がかからない配偶者の税額軽減制度があります。
法律上の配偶者ではない同性パートナーは、これも適用外です。そのため、法律上の配偶者であれば適用されるはずの「相続税の基礎控除」や各種の非課税枠が適用されず、高額な税金を支払わなければならない可能性があることを理解しておく必要があります。
生命保険を活用する際のその他の注意点

保険金の受け取りにハードルがある
被保険者が亡くなって保険金を受け取るためには、医師の死亡診断書が必要です。ところが、同性パートナーの場合、この診断書の取得に苦労することがあるという問題が存在します。 医療機関が死亡診断書の発行対象者を、配偶者や子どもなどの親族やその代理人に限定している場合が多いためです。
中には、パートナーシップ証明書を提出することなどにより、診断書が受け取れる医療機関もあります。また、保険会社の側もこうした事情を認識していて、例えば診断書のスムーズな取得のために医療機関への働きかけといったサポートを行う、とうたう会社もあります。契約の際に、そうした点についてもしっかり確認するのがいいでしょう。
パートナーシップ証明書の意味と限界
「証明書」が持つ意味
現在、日本全国で200以上の自治体が同性パートナーシップ制度を導入しています。この制度は、自治体が二人の関係を「公的に認める」ことで、様々な行政サービスや民間サービスが利用しやすくなることを目的としています。
ただし、一つ注意しなければならないのは、パートナーシップ制度は国の法律に基づくものではないという点です。 そのため、法的効力は伴いません。これは、たとえ証明書を持っていても、法定相続人になれないことや、税制上の優遇措置(配偶者控除など)を受けられないといった課題は解決しないことを意味します。
それでも、パートナーシップ証明書を取得することには大きな意味があります。これは、完全な法的保障ではないものの、「私たちの関係性を公的に認めてもらう」ための第一歩であり、「社会的信頼」を得るツールとして機能します。
具体的には、以下のようなメリットがあります。
- 公営住宅への入居申し込み:「家族」として認められ、申し込みが可能になります
- 病院での面会や手術の同意:多くの病院で、家族として扱ってもらいやすくなります
- 民間サービスの利用:生命保険や住宅ローンの手続きをスムーズに進めるための証明として利用できる場合があります
証明書がなくても利用できるサービスも
一方で、多くの民間企業では、パートナーシップ証明書がなくても、「生計を同一にする」という実態ベースの基準でサービスを提供するケースも増えています。
国の法律が「配偶者」という言葉に限定的な定義を設ける一方で、多くの民間企業や一部の自治体では、同性パートナーシップのニーズに応えようとする動きが広がっています。これは、法律は「民法の規定による配偶者」を要件としていますが、民間企業は「生計を同一にする」という実態ベースの基準でサービスを提供することで、法律が追いついていない領域で実質的な安心を提供しているのです。
このことは、私たちが「法律が変わるのを待つ」だけでなく、現時点で利用可能なサービスを賢く見つけ、組み合わせていくことが、二人の未来を守るための重要な戦略であることを示唆しています。
生命保険だけでは不十分? 遺言書と公正証書の重要性

遺言書は絶対に必要
同性パートナーにとって、遺言書は絶対に必要です。なぜなら、繰り返しになりますが、同性パートナーは法定相続人ではないからです。
遺言書がなければ、いくら長年連れ添い、財産を共に築いたとしても、パートナーに財産を遺すことはできません。遺言書は、大切なパートナーに財産を確実に引き継ぐための、唯一にして最も確実な法的手段です。
遺言書には、自分で作成する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」の二つがあります。
- 自筆証書遺言: 手軽に作成できますが、形式の不備で無効になったり、紛失・改ざんのリスクがあります。ただし、法務局に保管する制度を利用すれば、こうしたリスクを大きく軽減できます。
- 公正証書遺言: 公証人が作成するため、最も安全で信頼性が高い方法です。費用と手間はかかりますが、内容に法的効力が保証されます。
高齢の方だけでなく、若い世代の同性カップルも、遺言書作成は将来への備えとして大変重要です。
公正証書で関係性を明確に
公正証書とは、公証人が公証役場で作成する、強い法的効力を持つ文書です。遺言書だけでなく、同性パートナー間で「準婚姻契約」として作成することも可能です。
この契約には、もしもの時に備えて「財産分与」や「死後の事務委任」などを盛り込むことができます。公正証書は、パートナーシップ証明書よりも法的効力が強く、二人の関係をより強固に守るための重要なツールとなります。住宅ローン手続きなど、公正証書の提出を求める民間サービスも存在します。
パートナーシップ制度には法的効力がないという限界がありますが、遺言書や公正証書といった私的な法的文書を作成することで、そのギャップを埋めることができます。二人の関係を「口約束」ではなく「文書」で明確にすることは、未来の安心を築く上で最も重要なステップなのです。
よくある質問
Q: 住宅ローンは二人で組めますか?
はい、同性カップルでも二人で住宅ローンを組める金融機関は増えています。主な形態として、以下の二つがあります。
- 連帯債務型: 一本の住宅ローンについて、二人が共同で債務を負う形式
- ペアローン: 二人が別々に住宅ローンを組み、お互いが連帯保証人となる形式
どちらの形態も、お二人の収入を合算できるため、単独で借りるよりも高額な借入れが可能になるのがメリットです。ただし、どちらの場合も、不動産の名義は共有となるのが一般的です。そのため、もしどちらか一方に何かあった場合、その共有持分は法定相続人である親族に引き継がれてしまい、残されたパートナーが住居を失うリスクが生じます。これを避けるためには、遺言書での対策が絶対に必要です。
Q: 生命保険に入るべきか、貯蓄するべきか迷っています
二人とも働いていて、とりあえず先々の生活に困らないだけの経済力があるような場合には、わざわざ保険料を支払って生命保険に加入すべきかどうかは、要検討です。その分、貯蓄や投資などに振り向けるという選択肢もありますから、将来の生活設計をよく考えてみる必要があるでしょう。
ただし、生命保険には以下のようなメリットがあることも考慮してください。
- 万が一の際に確実にパートナーに財産を残せる(遺産分割の対象外)
- 相続税の納付資金や遺留分侵害額請求への対応に使える
- リビングニーズ特約など、生前給付の選択肢がある
おわりに〜同性パートナーとの未来を安心して築くために〜

同性パートナーとの未来を真剣に考えるとき、お金や制度の壁は、どうしても私たちの前に立ちはだかります。しかし、今回お伝えしたように、知恵と工夫で乗り越えられることがたくさんあるのも事実です。
同性パートナーを受取人とする生命保険が増えたことは、大きな前進です。しかし、税制面での不利や、保険金受け取り時のハードルなど、まだ課題は残されています。だからこそ、生命保険だけに頼るのではなく、遺言書や公正証書といった法的な備えを組み合わせることが重要なのです。
大切なのは、一人で悩みを抱え込まず、まずはパートナーとオープンに話し合うこと。「もし私に何かあったら、あなたはどうしてほしい?」「二人でどんな未来を築いていきたい?」といった会話から、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
そして、この記事を読んだことをきっかけに、生命保険の加入、遺言書や公正証書の作成といった具体的な行動を始めてみませんか?一つずつ、丁寧に、二人で歩んでいくことで、誰にも邪魔されない、私たちだけの未来を築いていけるはずです。
参考
- 【必読】LGBTが押さえておきたい生命保険の基礎知識とは?
- LGBTは生命保険に加入できる?同性パートナーが保険金の受取人に…
- 米国のLGBTQI+同性婚の課税を理解する – CDH – cdhcpa
- No.1195 配偶者特別控除 – 国税庁
- 生命保険の受取人は誰にする?結婚・離婚時などの変更方法は?死亡保険金の受取人に関する疑問を解説!
- ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン:LGBTQフレンドリー – 第一生命
- 「パートナー共済」 LGBTフレンドリーな総合保障 – 株式会社ダイバースパートナーズ
- LGBTQ を取り巻く社会・環境の変化と保険について
- 同性パートナーシップ制度とは?メリット・デメリットや同性婚との違いを解説 | スマート選挙ブログ
- パートナーシップ制度のデメリットは?メリットもシビアに網羅解説
- 鹿児島市パートナーシップ宣誓制度
- 愛知県ファミリーシップ宣誓制度について
- 【住宅ローン(新規)】事実婚あるいは同性パートナーの相手とペアで住宅ローンは申し込めますか? | よくあるご質問 – 三井住友銀行
- LGBT(同性)パートナーとの住宅ローン!条件からリスク対策まで完全解説
- 【司法書士解説】同性婚のパートナーが即実践すべき4つの法律手続き
- 同性パートナーへの遺言は公正証書にしないのも選択肢!リスクや費用で分析
- LGBT・同性カップルの財産管理には「任意後見」の活用がおすすめ!行政書士が制度内容を解説
- 同性婚と公正証書|カップルには気になる作成費用
本記事でご紹介する情報は、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。
各記事の日付はシステム上の更新日付であり、執筆時の日付と異なる場合があります。
各記事は、執筆当時の情報に基づいて作成されています。そのため、最新の情報とは異なる内容や、現在の価値観と相違する表現が含まれている場合がございます。ご了承ください。
また、当社は、読者様が本記事の情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。本記事の内容の正確性や個別の状況に関するご判断は、読者様ご自身の責任において行っていただき、必要に応じて専門家にご相談ください。